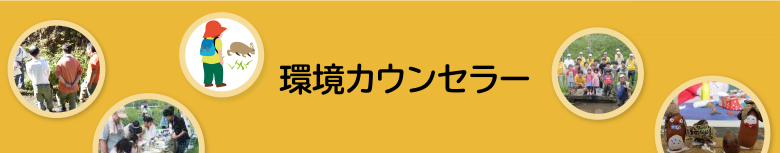| 登録年度 | 1998年度 |
|---|---|
| 氏名 | 芦ヶ原 治之 (ヨシガハラ ハルユキ) |
| 部門 | 事業者 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 70代 |
| 専門分野 | 地球温暖化、資源・エネルギー、公害・化学物質 |
| 主な活動地域 | 茨城県つくば市 |
| 主な経歴 | 環境・安全・衛生・品質管理など工場管理と電子用高分子材料の商品開発約33年。【資格】技術士(化学)、エネルギー管理士、EA21審査員、労働安全コンサルタントなど。【著書】共著「ISO安全・品質・環境早わかり」日本規格協、共著「小型貫流ボイラのトラブル対策」日刊工業新聞社など【講演】環境経営など多数回 |
| 特記事項 | ・一般財団法人省エネルギーセンターの省エネ診断員及び海外派遣登録専門家 ・EA21審査人:審査orコンサルティング ・講演:2014年2月「EA21を導入して環境経営」、2013年6月「原発と省エネ技術で国際貢献」他 ・共著書「ISO安全・品質・環境早わかり」ISO/OHS研究会 |
活動の紹介
地球環境とおうちの省エネ

つくば市梅園のみどり会(老人会)の要請で「地球環境とおうちの省エネ」のテーマで講演。“Think globally and act locally.” (地球規模で考え、足元から行動せよ)との視点で各自が環境を意識し、今日から小さなことでも取り組み始めることが必要と締めくくった。以前「おもしろ理科先生」の授業で使った「省エネの歌」(芦ヶ原作詞)を皆様で歌っていただいた。活発な多くの意見や質問があった。みどり会会報の抜粋を添付。
「秋の夜の虫の音会 in 金田台(こんだだい)の歴史緑空間(第19回歴緑イベント)」に参加
つくば市環境サポーターズのメンバーとしてご案内をいただき「秋の夜の虫の音会 in 金田台(こんだだい)の歴史緑空間(第19回歴緑イベント)」に参加。普段事業者部門としての活動が多いので、市民部門の活動に参加。普段聞きなれた虫の音の識別、歴史などを学び子供のころの虫の音とは違っているとの専門家の説明に驚きがあった。NPO金田台の生態系を守る会のメンバーとも久しぶりに交流。子供たちとの交流も楽しめた。
地熱利用の可能性調査
群馬県T村では地熱発電所の建設計画が持ち上がっている。K町はこの計画に反対している。T村の計画が実現すると、K温泉の源泉に影響を及ぼす可能性があることが原因。地球環温暖化防止への対策と現在の自然環境保全へ対策がここでは相容れないという結果である。地熱は全国どこでも同種の問題が潜在する。現状維持だけでは直面する地球温暖化対策に地熱を使うことはできない。このことを前提に地熱利用には抜本的な発想の転換が必要である。以上が今回の調査の結果である。
エコアクション21の審査と指導
環境マネジメントシステムの一つであるエコアクション21の審査とコンサルティングを担当している。中小の事業所がマネジメントシステムにのっとった活動をし、認証を得ているが、その内容の審査に現場確認に伺う活動である。計画Pー実行do-確認check-修正Actionのサイクルが順調に廻せていること、できていないところは指摘事項として取り上げその修正確認まで実施することで認証継続を推奨する。このことで自然環境改善に寄与。
省エネ法指定工場における実績の上がる省エネ対策による法令順守の支援
省エネ法指定工場の中小事業所の主にエネルギー削減による法令遵守のための支援を複数社実施を継続。省エネチームをコアとする会議に部署別に現場の責任者に参加いただき、討議をすることで地に足ついた省エネ項目の発掘の支援に心がけている。担当者のモチベーションの向上には省エネ会議への参加は有効で、更に成果を数値で表すことで、張り合いを持っていただけていると思われる。
環境省のSHIFT事業の「省エネ診断」
環境省のSHIFT事業の「省エネ診断」を茨城県の某印刷会社で実施。太陽光発電設備の導入も含めていくつかの提案をした。このSHIFT事業における省エネ補助金の申請条件にこの省エネ診断が含まれている。
エコアクション21(EA21)の審査及び支援
EA21の審査活動を2023年度も複数件実施。2017年度版のガイドラインの改定以来、経営への支援要素が増えている。審査の際、環境マネジメントシステムの運用について丁寧な支援もすることが求められている点がISO14001と大きく異なる点の一つである。費用が安いばかりでなく、受審者側にとっては大いに有利な点である。
月刊「食品工場長」8月号に「改正省エネ法のポイントと食品製造業の対応策」のテーマで寄稿
改正省エネ法の趣旨とその概要を解説し、食品製造業として向かうべき方向と、特に今回の改正された省エネ法にマッチしている設備と利用の事例を紹介する。
国としての脱炭素への取り組みの方向性は2050年のカーボンニュートラルに向けて①省エネを強化し、②非化石エネルギーの導入拡大を進め、化石エネルギー使用量の極小化を図る。最後に残存するCO2はCCS、DACCS、BECCSなどの技術を使いトータルゼロを目指すという取り組みの方向性を示したものである。詳細は本紙を参照いただきたい。
省エネ提案と今後について
埼玉県・茨城県省エネ促進プラットフォーム事務局にて専門家として地元中小事業所の省エネ診断を担当。半導体製造装置周りの特殊部品を製造しており、大手客先の仕様で対象製品の製造設備を含めて、原則一切変更は認められないと云う条件でした。省エネ提案10項目と補足提案1件を報告。全体を通して①現場の方の環境意識改革、②各職場代表による省エネチームを作り毎月一回程度の頻度でPDCAを回す活動の実施。③広い経験を持つ省エネ専門家の知恵を借りる。などの提言を致しました。
省エネ及び環境経営の着眼点
地元の中小建設業への環境マネジメントについての指導・助言の機会をいただきました。主に設計事務所からの請負仕事の為、工法など良い案があっても仕様が変えられない為環境活動にどう取り組むかについての相談の要請をいただきました。①まずは今できることをリストアップし実施を始めること。②現場の方の環境意識改革の取り組むこと。③優れた提案はしっかり吸い上げ、設計事務所に提言すること。⇒結果として次の受注に結びつく強みに繋がることなどを提案致しました。
省エネ法遵守と省エネのPDCA
地元の鉄の加工を主な業務とする中小企業で省エネ法の順守を中心に助言をさせていただく機会をいただきました。鋼材を高温にした後で加工する工程ですが、長期に渡り使用してきた設備への変更提案は、設備メーカからの品質保証の観点から許可がおりません。これが事業所全体の約2/3のエネルギーを消費しており、残りの1/3で毎年全体の1%の省エネ削減を積み上げてゆくのは大変です。省エネチームに参加し、昨年はコロナ禍で売り上げ低下でBクラスに転落しましたが、Sクラス奪還の目途がたちました。
雑誌「地球温暖化」への寄稿:〈題〉食品製造業でできる省エネ対策 その2(熱管理)
食品製造業におけるエネルギー使用量は冷蔵・冷凍用電力とボイラー用燃料が大半を占めます。今回はボイラの省エネ対策全般として18項目を挙げ、重要な項目を示し、中でも特に有効な2例を選んで解説。著者自身の共著書である「小型ボイラのトラブル対策」日刊工業新聞社、より多くを引用しており、詳しくはそちらを併せてお読みいただくことをお薦めします。ボイラの省エネは簡単な知恵で大きな経費削減になる項目があります。そして化石燃料削減に大いに有効です。
講演「地球温暖化は止められるか」
地球環境の現状紹介、パリ協定など世界における地球温暖化対策への動きを紹介。誰もまだ完璧な解決策を持っているわけではなく手探り状態である中で、本質的な問題点に切り込んだ『 人新世の「資本論」 』 (集英社新書)斎藤 幸平氏著が話題になっていることを添え、まずは皆様ご自身が、広く情報入手に心がけ、自らの足元からできることに取り組むことが求められていることを訴えた。
地域プラットフォーム支援事業としての省エネルギー診断
事業者様からの要請で省エネ診断とその説明会を実施。社内での省エネ意識は高く、データの整理はできていても、専門家の目から見るといろろ不十分な点が認められ、ポイントを絞って11項目を提案。特にこの報告を如何に実施できるかが重要でマネジメントシステムとの組合せが有効である旨説明。省エネは費用だけでなくCO2削減効果もしっかりメリットとして認識する必要があることも添えた。
EA21更新審査と省エネによる経費とCO2削減のアドバイス
環境マネジメントシステムであるEA21(エコアクション21)の審査実施時に具体的CO2削減法についての要請に答えて、コンプレッサ圧の適正化、車両の燃費向上における具体策などデータのとり方も含めて対策をアドバイス。
EA21更新審査と省エネによる経費とCO2削減のアドバイス
環境マネジメントシステムであるEA21(エコアクション21)の審査では水使用量の異常値の原因解析と対策をアドバイス。要請に答えてボイラ周りの保温の有効性、ボイラとコンプレッサ共に圧力設定値による無駄について指摘と具体策をアドバイス。
効果的な省エネ改善事例
多くの省エネ診断を実施してきた中で、決まりきったパターン以外の診断者として印象に残った事例をいくつか研究会で紹介。省エネ診断員や企業関係者の方も多い中、手応えを感じることができた。
ポテンシャル診断事業としての省エネルギー診断
事業者様からの要請で省エネ診断とその説明会を実施。工場単位では省エネ法第二種指定工場対象ではないが近い状況。13項目と計測診断2か所を実施。まだまだ省エネの余地は多くみられる。太陽光発電もすでに導入済だが、更に既存の2倍の導入を提唱。こちらも報告を如何に実施できるかが重要でマネジメントシステムとの組合せが有効である旨説明。省エネは費用だけでなくCO2削減効果もしっかりメリットとして認識する必要があることも添えた。