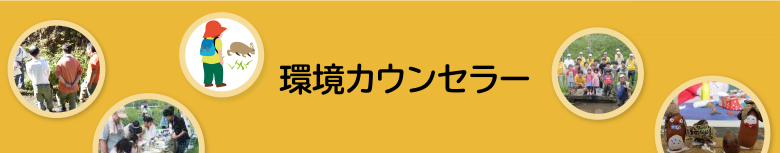| 登録年度 | 2003年度 |
|---|---|
| 氏名 | 召古 裕士 (メシコ ヤスシ) |
| 部門 | 市民 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 70代 |
| 専門分野 | 自然への愛着、生態系・生物多様性、地球温暖化 |
| 主な活動地域 | 島根県松江市 |
| 主な経歴 | 環境コンサルタントで学んだ知識と経験を活かして、持続可能な社会を創るためにNPO法人日本エコビレッジ研究会の活動や講演、協働作業を通じて地域社会の活性化を推進して行きます。また、東南アジアや欧州への視察を通じて、得られた知見から環境教育への助言や循環型社会への提言を行っています。 |
| 特記事項 | 技術士(総合技術監理部門&建設環境)・コミュニティービジネスなどの資格や経験を活かし、産業創生や雇用創出へ繋がる事業を環境に配慮しながら推進したい。 |
活動の紹介
小波浜の貝砂の素晴らしさと不思議
尾道市の重井中学から依頼を受けて、14名に出前講座を行った。小波浜の貝砂の素晴らしさと不思議、海ごみを通して環境問題のお話をしました。
終了後、ユネスコスクール・キャンディデート承認校の委員会に参加し海の楽校の取り組みについてお話ししました
壊れた環境を取り戻すにはどうしたら良いでしょう?
浜田市より依頼を受けて浜田市で8名に浜田地域環境サ-クルへ出前講座を行いました。壊れた環境を取り戻すにはどうしたら良いでしょう?と言うテーマでお話をしました。自然環境とは?山と海の関係は?そして、今の海はどうなっているの?などのお話をしながら、沿岸部の痛みや豊かな沿岸部の悩み、さらに地球環境が直面している課題や地球環境への影響などの学習の上に自然環境を取り戻すにはどうしたらいいのか?をお話ししました。
「海ごみ」学習会
島根県連合婦人会より依頼を受けて、大社コミュニティーセンター&長浜にて20名の皆様へ「海ごみ」学習会を行いました。
出雲市長浜には漂着物が絶え間なく打ち寄せてきます。海ごみの回収を続けておられる方々に、海ごみについて幅広い視点から学んでいただきました。さまざまな毒性を持つごみなど暮らしと結びつけてお話ししました。また、近くの浜に出掛けて海ごみの回収を行いながら現地でのお話もさせていただきました。
島根半島の素晴らしさと不思議
島根町公民館より依頼を受けて、海の楽校で20名の皆様に、島根半島の素晴らしさと不思議について学習会を行った。出雲国が栄えたのは、島根半島が作り出した風土によって歴史や文明文化が築かれたことや小波浜の砂に微小貝がたくさん含まれているのはなぜなのか?高齢者の皆さんが驚くようなお話をさせて頂きました。私たちが暮らす足元の素晴らしさと不思議を感じてもらいました。手作りの
懇話会を開き、手作りのお茶とぜんざいでオモテナシ!
日本海や島根半島や小波の不思議
SKの依頼で「さかなクンのおさかな教室in山陰」に参加し1500名入場中約100名程度を対象にさかなクンの前座を務めた。日本海や島根半島や小波の不思議をお話ししながら、小波浜の微小貝をデジタル顕微鏡で観察しながら生き物の素晴らしさと不思議を体験してもらった。
宝石のような微小貝に親子で驚きながら、生物の多様性を感じてくれたようでした。
ジオパーク各論(地域振興・観光)

学内で72名対象に講義を行なった。島根半島は、激しい季節風から出雲国を守り対馬暖流や山地より流下する河川の恵みを受けて豊かな社会空間を築いた。これら自然の摂理に基づいた文明文化の発展の経緯、環境保全や教育を踏まえたジオパークへの取り組みなどお話しした。
体験環境学習&ワークショップ

環境省松江管理官事務所の依頼を受けて、小学生高学年13名を招いて「海の楽校」を開催した。ビーチコーミング(浜辺の観察)や採取した小さな貝でアクセサリーやジオラマを作り、昼食時にはウニのお話と食べ方について漁師永見さんのお話を聞いた。こうした自然を楽しむ体験を加えるなど海を楽しんだ。
自然体験誘客促進事業

海の体験学習ワークショップ&SDGs学習を親子20組44名招いて2日間にわたっておこなった。自然体験誘客促進事業では新たに微小貝40種の写真標本を作成し、微小貝のメッカとして観光資源を用意した。また、BSSとSDGsパートナー企業が豊かな環境を守るSDGsを学びながら自ら環境を守る宣言を行った。パートナー企業を迎えて、事前に環境学習の時間を取って相互に学ぶ機会を作った。
環境体験学習

サイエンスに興味深い子たち44名が参加する環境体験学習を開催した。松江市内の学習塾との協働企画で、コロナ明けの活動が行われました。生きる力の一つ炊飯なども交えて、自然観察や生物調べなど生物の多様性を学ぶ有効な機会を用意した。今年で3年目のコラボです。ここでも、親子参加促し効果ある体験が行われたと感じました。
ミクロの世界は神秘的な美しさ

大山隠岐国立公園満喫プロジェクト島根半島東部協議会及びTSK海と日本Pro.協働事業を63名の児童を招いて行なった。
ビーチコーミングと室内学習、アクセサリーorジオラマづくりを通して、砂浜の中に微小な生物の世界があり、その多様性や豊かな環境を学んだ。貝合わせ約110種の標本を作り、子どもたちが採取した貝の名称を調べることができるようにした。
ジオパーク概論
1月25日ジオパーク概論で、47名を対象に校内で講義をおこなった。島根半島が、北西の季節風から郷土を守り対馬暖流や山地より流下する河川の恵みを受けて豊かな社会空間を築いたことや出雲地方の風土や暮らしについた内容。加えて、過去1年間環境の保全や教育を踏まえたジオパークへの取り組みなどの内容とした。
海の楽校
メディアBSSの依頼を受けて11月3日「海の楽校」で、親子10組に向けて、環境体験学習「海の教室」をスポンサー5社の応援を受けて行なった。内容は、SDGsについて学びを深めようと実際にビーチコーミングやアクセサリーやジオラマ作り体験をした。参加者よりスタッフの方がはるかに多く、これを通して一緒に学んだ。
海の楽校
6月28日コロナ禍ではあったが、持田小学校4年生の生徒56名が「海の学校」に大型バスでやってきた。環境学習や清掃活動について学んでくれた。中でも、打上げられた砂の多くが貝殻でできている事やその中に微小貝が沢山いることをデジタル顕微鏡で見つけ大変驚いてくれた。微小貝の観察を通じて生物の多様性を学んだ。
美保関町ジオパーク学習会
4月20日 15名の皆様を対象に島根町の松江ビジターセンターにてジオパークを展示と座学で学び、続いて多古鼻まで移動し現地の視察をしながら自然環境と現在の発展における繋がりを学習した。さらに、小波海岸にて漂着ごみや環境保全について学び、最後は郷士の地域愛につながる千酌海岸を訪ね学習会を終えた。
海の楽校
春休みから夏休みと断続的に「海の楽校」で、約100名の小学生に海の自然観察や収集した貝殻でジオラマやアクセサリー作りを体験した。打上げられた貝殻から前浜の環境を推定しながら環境の豊かさや大切さ学んだ。毎回、終了後は浜の清掃活動を行い保全の大切さも学んだ。小学3年生以下は保護者同伴とし混乱を予防した。
ジオパーク学各論 ジオパークで地域振興・観光
1月25日コロナ禍の島根大学でリモート講義40名を対象に講義。島根半島が、北西の季節風から国土を守り対馬暖流や流下する河川の恵みを受けて豊かな社会空間を築いたことや出雲地方の風土や暮らしについて講義した。また、環境の保全や教育を踏まえたジオパークへの取り組みなども加えた。
なぜ出雲国が栄えたか
11月29日出雲商工会議所で、30名に「なぜ出雲国が栄えたか」をタイトルに講演を行なった。出雲平野と宍道湖中海の汽水域が食と交流を支え豊かな出雲国を創り出す事が出来た。その結果、出雲大社、日本酒や相撲、歌舞伎などの発祥の地として栄えて来た。環境を守り繋ぐ大切さを講演した。
島根町多古鼻エコツーリング
10月25日出雲から7名を迎えて島根町の地元エコツーリングを行なった。多古鼻の先端から小波の浜まで、歩きながらジオストーリーや生物環境、サザエのおにぎりを試食しながら地域の暮らしや地元の人による「かなぎ」サザエ漁のお話など丸1日のツアーで豊かな環境と暮らしを学べたと高評価。
打ち上げられた貝殻でアクセサリー作り
8月9日急遽接近する台風下、小学生10名がビーチコーミングで収集した貝殻を使って海の楽校でアクセサリー作りを行った。色や形をデザインしたり生物の暮らしぶりを学習したり小波のお話を交えた工作は、環境と保全の大切さを学ぶ体験活動、コロナ禍だったが良いプログラムが出来た。
海の楽校 ビーチコーミング
7月26日より断続的に5回に亘って62名の小学生に海の自然観察を島根町の小波で行った。コロナ禍で三密を避け暑い夏に日差しを浴びながらのマスクはかわいそうだったが、打ち上げられたゴミや生物の観察を通して夏の思い出が作られた。環境の豊かさと保全の大切さを学んだ。