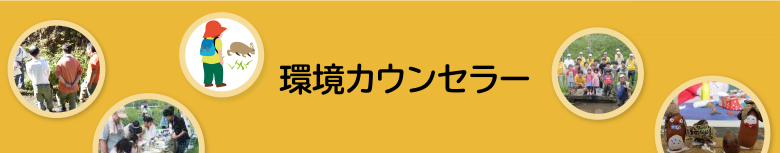| 登録年度 | 2014年度 |
|---|---|
| 氏名 | 中西 一成 (ナカニシ カズナリ) |
| 部門 | 市民 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 60代 |
| 専門分野 | 生命、自然への愛着、生態系・生物多様性 |
| 主な活動地域 | 兵庫県川西市 |
| 主な経歴 | ・NPO法人野生生物を調査研究する会に所属し、自然観察会やセミナーの講師を務める。・川西市高齢者大学の講師を務める。・猪名川町小学校理科部会会長として教職員研修を推進する。・猪名川町環境教育研究会会長として自然調査保全活動を進める。・大阪府水生生物センターサポートスタッフとして活動する。 |
| 特記事項 | ・「生きている由良川」「生きている淀川」の発行共同著者・兵庫県小学校教育研究会理科部会理事・猪名川町環境教育研究会会長・日本魚類学会会員、日本陸水学会会員 |
活動の紹介
猪名川学シンポジウム第2回「持続可能性の教育とは何か」
持続可能な発展のための教育(ESD)の実践事例を紹介した。マイクロプラスチックによる海洋汚染に立ち上がった世界の若者たちの動き、兵庫県の高校生のプラスチックごみのルート研究、猪名川町の中学生の大阪湾からアユを遡上させるためのプロジェクトなどを紹介した。ゲストの大阪公立大学の伊井直比呂先生からは、若者たちのESDが地域の主体者として生かされるための環境づくりについて講演された。ユネスコスクールの取組も紹介された。
猪名川学シンポジウム第1回「探究的な学び・猪名川学とは」
第3期猪名川町教育振興基本計画の中心となる総合的な学びの構想としての「猪名川学」について、町民全体の理解を深めるために、一般社会人対象のシンポジウムを開催した。私からは、探究的な学びの魅力、その構造と進め方について講義した。ゲストとして奈良教育大学教授の中澤静男先生からはESDについて講演していただいた。
猪名川学入門講座(中学校教員対象のセミナー)
和7年度より展開する猪名川学(猪名川町小中学校総合的な学習の時間を中心に実施)は、猪名川町全体を学びのフィールドにして、探究的な学びをグローカルに展開していく構想である。そこで、小中学校の教職員を対象に、猪名川学の基本的な学びのイメージを講演した。
猪名川アマゴ供養祭に協力
猪名川漁業協同組合が行うアマゴの放流行事に参加した。アマゴの放流を直接行った。猪名川漁業協同組合の活動状況を聞き取り、一庫ダム上流の大路地川や田尻川におけるダム湖産アユの状況を確認した。
多田銀銅山の調査「佐曽利カルデラと鉱脈」
人と自然の博物館セミナー「いしころクラブ」の自然観察会に参加し、猪名川町小中高校生対象の学習講座の開催に向けた下調べを行った。中生代の噴火活動を物語る佐曽利カルデラの外側の丹波帯の岩石、カルデラの流紋岩、カルデラ湖に堆積した泥岩などを歩きながら体感した。鉱山内の鉱脈も確認した。
宝塚市環境基本調査「中山足洗川」
宝塚市より自然環境の全市にわたる調査の依頼を受け、阪急中山駅北側に位置する中山足洗川の水質調査および生き物調査を行った。
宝塚市環境基本調査「最明寺川」
宝塚市より自然環境の全市にわたる調査の依頼を受け、JR川西池田駅南側に位置する最明寺川の水質調査および生き物調査を行った。
宝塚市環境基本調査「逆瀬川上流」
宝塚市より自然環境の全市にわたる調査の依頼を受け、阪急電鉄逆瀬川駅の西側に位置する逆瀬川上流西山橋周辺の水質調査および生き物調査を行った。
宝塚市環境基本調査「仁川弁天池」
宝塚市より自然環境の全市にわたる調査を私が所属するNPO法人野生生物を調査研究する会に委託された。私は主に水環境について担当しポイント毎に化学調査と生き物調査を行った。阪急電鉄仁川駅の西側に位置する仁川弁天池の水質調査および生き物調査を行った。
大阪体育大学教育セミナー「ESDとは何か」
大阪体育大学教育セミナーで教員を志す大学生を対象に、ESDについての講演を行った。環境教育は1992年を起点として大きく変わり、「持続可能な発展のための教育(ESD)」に転換した。持続可能性を考える具体的な視点や展開の方法について、具体的な実践事例を用いて話をした。
環境教育指導者セミナー⑥森林と動物
季節と共に変化する里山の様子を紹介し、遠目で見て観察する方法を紹介した。日本の森林行政の特徴や森林分布を説明した。水源涵養、土砂災害防止、大気浄化、生物多様性保全、気候緩和、物質生産、保養レクレーション等の森林の持つ働きをまとめた。動物では主にシカの食害と土壌流出について話をした。里地里山の荒廃のメカニズムについても解説した。
環境教育指導者セミナー⑤徳島眉山の里山観察会
眉山は徳島市民にとって母なる山で週末には多くのハイカーが訪れる。江戸時代も徳島藩の里山と開かれ、里山としての魅力がある。眉山天神社の山道から観察会を行った。境内の裏山はムクノキ、シュロ、イヌビワなどの樹林の中、オカメザサ、ノシラン、コヤブラン、テリハヤブソテツ等、暖地性の山野草が多かった。
環境教育指導者セミナー④諫早湾干拓問題など
諫早湾に巨大な堤防をつくり、干拓用地を設けた長崎県の施策の是非が問われた大きな環境問題を開設した。陸地からの栄養の供給がなくなったことで、諫早湾の漁業は衰退した。世界にはこのような事例が多数あることも紹介した。
環境教育指導者セミナー②鮎喰川調査
徳島市に流れる吉野川の支流「鮎喰川」の河原にて、川の生き物調査を受講者に体験してもらった。河原の植生観察、川の生き物採集、河原の岩石観察を行った。受講者は、それぞれの専門指導者によって、観察を通して知識を広げ、講習会の開き方を学んだ。
環境教育指導者セミナー①環境教育の歴史
自然観察会から自然の不思議や魅力を感じる自然学習から始まり、1970年代には公害問題に直面し、環境教育は様々な側面をもって発展してきたが、
経済問題や社会問題と統合した「持続可能な発展のための教育(ESD)」となった。(1992年リオデジャネイロ国連総会)
森里川海連環学入門⑤人の体の中の魚
私たちの祖先を辿っていくと、硬骨魚類にさかのぼる。私達の体は背骨を中心に様々な骨格が発達して筋肉がついている。昆虫などの外骨格ではない。
3億6000万年前に陸に上がった魚は哺乳類へと進化した。
森里川海連環学入門④日本の里山の課題
化石燃料の使用によって、薪炭林は放置され、里山は荒廃している。その結果、奥山化し野生動物が人里に下りてくるようになった。また、生物多様性も減退している。特に、シカの食害は深刻な問題となっている。
森里川海連環学入門③なぜ漁師が山に木を植えたのか
宮城湾の牡蠣の復活に力を注いだ畠山重篤さんのお話を紹介しました。気仙沼湾の奥の室根山に広葉樹を植えたことで海は蘇った。落ち葉のフルボ酸鉄のメカニズムは世界のSATOUMI理論となった。
森里川海連環学入門②回遊魚の生態学
川を上り下りする魚の種類について紹介しました。ウナギなどの降河回遊魚、サケなどの遡河回遊魚、アユなどの両側回遊魚について、その特徴をお話ししました。主に、サケ科のアマゴとサツキマス、ヤマメとサクラマス、イワナとアメマスなど、陸封型と降海型について理解を深めました。
森里川海連環学入門①川は生きている
徳島大学人と地域共創センター社会人講座で、環境教育の基礎的な知識を楽しく学習する講座を土曜日10:00~12:00に開講しました。徳島市、小松島市、北島町等から社会人あいあが参加しました。第1回目は、川の構造、川が作り出す自然環境、川の生態系、生物同士のつながりなどを講義しました。
「魚類進化のはてな?」
人間のご先祖様は、硬骨魚類です!約6億年の歴史を早回わしでお話ししました。いわしと鯛とウナギではどちらが新しいタイプの魚でしょうか?これからは、煮魚や焼き魚を食べるときには、じっくり骨格を身ながら食べるようになることでしょう。
「せみのはてな?」
セミは昆虫の中でも一番大きな鳴き声です。フランスの昆虫学者ファーブルが観察した時、とても驚いたお話を紹介したり、土の中での暮らしぶりについてみんなで考えてみました。また、からだのつくりからカメムシの仲間であることが理解させた。日々の観察の方法をいくつか提案した。
「へちまのはてな?」
「へちまのはてな?」(7/11)、「へちまを食べよう」(8/7)、「へちまたわしをつくろう」(9/5)、「へちま水を取ろう」(10/11)の4回シリーズで、地球の環境にやさしい“へちま”の栽培とその活用について講座を展開しました。参加者は実際にへちまの実を体験し、ウリ科植物の不思議な性質を体験して感動していました。
メダカのはてな?
京都市伏見区南部はかつての巨椋池や横大路沼の干拓地である。都会化が進むこの地域の水路を調査した結果、在来種のミナミメダカやモツゴ等と、外来魚のカダヤシ、タイリクバラタナゴなどを採集した。水槽観察して解説を加えた。参加者は、日本の生態系はかなり外来種の侵出が進んでいることを理解し、自然の課題を学ぶことができた。
猪名川の水環境と生き物
猪名川の河川環境を主に、①水質、②縦断連続性(水陸移行帯、河原、湿地の減少)、③縦断連続性(流量の減少、瀬切れ、地下流、井堰、ダム、魚道の未整備)④外来生物の侵入(オオクチバス、ブルーギル、ウシガエル等)の視点で分析するとともに、森里川海のつながりを様々な生き物の立場から解説した。
さすてないきもの探偵団

京都市南部クリーンセンター環境学習施設「さすてな京都」のこども学習プログラムにおいて、地域の伝統、歴史文化、地域の生物多様性を土台にした環境学習プログラムを実施している。地域の水辺の生き物、地域の野鳥や渡り鳥、土の中の生き物などを題材に講座を実施した。
川西市高齢者大学「猪名川の水環境と生き物」

かつては水質で全国ワースト1であった神崎川(猪名川の下流)の水質も改善されCODもかなり改善された。しかしながら、かつての豊かな循環が復元されたわけではない。どこに課題があるのかを探った。
川西明峰高等学校「明峰の学び」森川里海連環学

森川里海のつながりを基軸に循環型社会をローカルからグローバルに考える環境学習を4回シリーズで展開した。1~3回目までは河川回遊魚を指標にした河川の水環境を中心に授業を進め、4回目は高月紘先生の環境マンガをつかって環境道徳授業を展開した。
河川の生き物

三田市高齢者大学講座を担当し、「河川の生き物」というお題をいただき、
身近な淡水魚を中心に生態系全体の理解が深まる生き物のつながりについて
楽しいお話しを展開した。
兵庫の河川の魚講座

兵庫県内水面漁業組合連合会のイベントにおいて、参加した親子を対象に、兵庫県の川で採集した魚の水槽展示を活用して、淡水魚の進化にふれながら、生物多様性の大切さについてお話しをしました。
川西明峰高校「明峰の学び」講座「森里川海の連環学入門」

「明峰の学び」講座にて、「森里川海の連環学入門」を行った。(計4回)
今日の環境問題は、森、川、海のつながりを考えた環境概念の重要性が指摘され、相互につながり循環しているシステム思考が求められている。
加古川上流の東条湖のアユ(ダム湖産アユ)について

加東市ノーベル大賞(夏休み自由研究)の受賞発表会にて、記念講演を行った。加古川上流の東条川の支流鴨川ダムに再生しているアユについて、その実態について講演した。西日本の温かいダム湖で起こっている陸封アユが生まれている現象についてお話をして、今後の地域の宝物にしてほしいと締めくくった。
一庫ダム湖産アユの産卵場づくり

一庫ダムに再生している陸封されたアユの育成のため、田尻川、一庫大路次川の両河川の産卵場を造成した。参加者は、水資源公団職員、川西市職員、NPOなど、地域を支える関係者を対象に講習と実践活動を行った。
猪名川の魚類調査(夏休み子ども教室・国交省猪名川河川事務所主催)

国交省猪名川河川事務所主催の夏休み子ども教室を猪名川の魚をテーマに計5日行いました。中流域の淵、瀬などの川の地形に棲む魚の姿を観察しました。何を食べるのかで棲んでいる場所が違うことを学びました。
大阪湾に棲む稚アユを調べる

猪名川、武庫川で産卵孵化した仔魚は、大阪湾に下り翌春、川を遡上するはずである。現在は放流アユによる河川管理が行われているが、天然遡上のアユの実態をつかむために、猪名川町の六瀬中学校ふるさとクラブが冬の甲子園浜で稚アユの採取に臨んだ。
猪名川下流藻川でのアユの産卵床づくり

国土交通省猪名川河川事務所からの依頼を受けて、尼崎市中園橋上流にてアユの産卵を助ける河原の造成を地域の住民と共に行った。集まった多くの小中学生や自治会の皆さんに、アユの生活史と産卵床の作り方について講習した。
川西市高齢者大学講座「猪名川の漁業 SATOUMIとともに」

毎年講演している川西市高齢者大学講座で今年は、海と川のつながりを中心に講演した。下流で産卵したアユは一生を終え、孵化した仔魚に命をつなぎます。4日以内に海に下り4ヶ月間海水で過ごした稚アユは川の水温が上がるのを機に遡上を開始します。海でいかに育っているかを皆さんと一緒に考えました。答えは尼崎の海の調査、そして甲子園濱へ。
兵庫県内水面漁業の今後の展望 アユの未来

兵庫県内水面漁業連合会のシンポジウムにパネラーとして参加し、多面的事業について討論した。市民とのふれあいができる川のあり方を探った。市民とのふれあいを今後様々な形で行って、地域に愛される川づくりについて、活発な討論会になった。アユの基本遡上量を増やす取組についても意見交流した。
猪名川一庫ダム湖産アユの遡上観察会

一庫ダムで自然再生しているアユが年々増えている。かつてはダム建設による自然再生調査の一貫でダムの上下で試験放流していたものが、上流にて定着したと考えられる。森下郁子先生(大阪産業大学名誉教授)によれば、水温が4℃を下回らなければ可能と判断されている。ダム湖での生態について六瀬中学校ふるさとクラブを率いて調査している。
大阪湾サーフゾーン生き物調査

大阪湾の砂浜を調査し、その生物多様性についての研究活動を中学生と共に行っている。埋め立てにより、自然海浜の割合は4%まで減少し、わずかに残っている甲子園浜などで生き物調査を行っている。海の魚の仔稚魚だけではなく、アユの仔稚魚も観察している。
川西市高齢者大学講座「猪名川の回遊魚」

大阪湾に注ぐ淀川水系の一級河川「猪名川」を上り下りするアユ、ウナギ、モクズガニなどについて、紹介した。流域の自然、水質の変化や堰などの構造物と遡上の関係について触れた。
兵庫県内水面漁協総会「水辺の生き物観察会」

兵庫県の漁業協同組合の総会および研究大会に先立ち、会場(市川支流)に於いて水生昆虫を中心にした水辺の生き物観察会を行った。親子連れの参加者に、川の生態系について学習会を行った。
猪名川の生き物再発見(猪名川町自然講座)

猪名川に生息する魚類を中心に生息状況を解説した。魚類の進化の歴史やそれを元にした生物多様性について紹介した。また、魚類の解剖を行い、人間の進化上の祖先である魚類の体の構造について解説した。
猪名川下流域の中学校とのアユの合同観察会

猪名川の下流域の尼崎市立成良中学校ネイチャークラブはじめ3中学校の生徒を招待し、六瀬中学校ふるさとクラブと合同観察会を行った。主に、放流アユの捕獲と解剖、消化器官の内容物を顕微鏡で観察し、食性を分析した。
猪名川におけるアユの放流観察

六瀬中学校ふるさとクラブを指導して、アユを放流し生育状態を観察している。藻類調査、水生昆虫調査、魚類調査、植物調査を定期的に調査し、アユが住む環境として多面的に考察した結果を地域に発信している。
「淀川の魚」水槽展示会
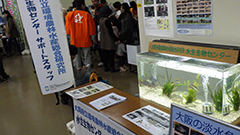
大阪広域水道企業団主催「来て見て体験in村野浄水場」のブースとして、大阪府水生生物センターサポートスタッフとして解説員を務めた。淀川は日本でも有数の魚種の多い川で、城北ワンドや庭窪ワンドなどに住む魚種を中心に解説しました。
(水槽の数が少なかったのが残念でした。)
「猪名川水系の魚」展示学習会
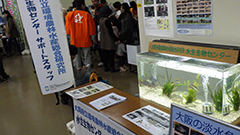
川西市主催の黒川水辺まつりのブース(川西市立黒川公民館)にて10:00~14:00、上流、中流、下流に大別した水槽に、流域の魚を展示し、来場した子どもたち、親子連れから質問に答えながら、水系の淡水魚を解説しました。特に、モクズガニやウナギ、オラニラミなどが人気でした。
「アユの産卵床づくり」
阪神北県民局主催、武庫川漁業協同組合共催の行事に、六瀬中学校ふるさとクラブを参加させて、アユの生活史について理解を深め、猪名川での実践にいかせるよう、指導しました。武庫川の場合、河口付近まで清流が続き、産卵に適した環境があります。
「魚類標本の作り方」
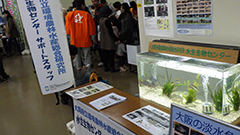
川西市高齢者大学自然コースの講座(於:川西市文化会館、受講者38名)で、液浸標本の作り方を講義しました。猪名川に住む淡水魚を使って実際に参加者一人一人が標本を作製しました。標本の持つ意味や見方などを補足し、猪名川水系の魚類の実態について説明しました。
アユの放流実験
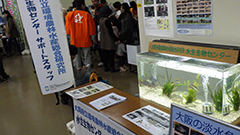
六瀬中学校ふるさとクラブを指導して、猪名川上流漁業協同組合、揖保川漁業協同組会の協力のもと、猪名川万善佐保姫公園下にてアユ10kgを放流しました。約三ヶ月半、その生育調査を行い、アユの遡上について考える小中学生を指導しました。