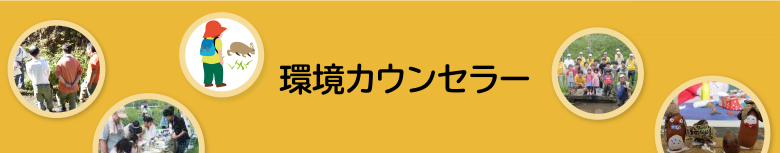| 登録年度 | 2021年度 |
|---|---|
| 氏名 | 大庭 靖史 (オオバ ヤスシ) |
| 部門 | 事業者 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 60代 |
| 専門分野 | 生態系・生物多様性、地球温暖化、産業 |
| 主な活動地域 | 大阪府 |
| 主な経歴 | 自動車製造の国内/海外での工場運営・生産技術経験を活かし、国内外グループ会社のSDGsやCNを目指した長期環境取組みプランを立案、各社と協力し推進。現在は、官農工連携による持続可能な地域のしくみ作りを、各省庁・地方自治体・地元有識者と協業して推進中。2003年からEMS主任審査員。 |
| 特記事項 | 環境マネジメントシステム主任審査員 品質マネジメントシステム審査員補 IEMA(UK) EMS Auditor、Environment Auditor (2004~2010) 日本自動車工業会 環境委員会委員(2015~2020) 関西経済連合会 エネルギー・環境部会 委員(2014~2022) |
活動の紹介
地域資源循環システムの実証試験プラントの工程設計~量産立上げ
地域のバイオマス資源=牛糞からCN燃料を創出し、残渣から堆肥・液肥を生産、耕種農家が活用、耕作による稲藁を牛の飼料に活用し、地域資源の循環に取組み。
推進地域で飼育される牛は肉牛であり、乳牛で発酵技術が確立された湿式発酵が使えない。また、琵琶湖が近い滋賀県では、大量の液肥を耕作地に施用することが難しい。そのため乾式発酵技術を所属企業内の技術者で開発した。
また、技術が確立済の湿式発酵ではないため、工程・設備の技術が無く、自動車生産ラインのノウハウを活かして、自社独自の発酵プラントを構想し、具現化した。
地域資源循環システムのCOP28での展示・プレゼン

環境カウンセラー試験・小論文で考え方を示した、企業が参画する地域資源循環システムについて、COP28@ドバイ・UAEのJapan Pavilionに於いて、「Together for Action」の事例として展示・説明を行った。
地域行政がリーダーシップをとり、農業分野と工業分野が地域で協業することで、資源循環を起こし、カーボンニュートラルと有機農業の拡大につなげるサステナブルな取り組みは、COPの場でも多くの国の多くの方々の賛同が得られ、この着想の価値を共有することが出来た。
地域資源循環システム構築へのSDGs企業の主体的参画
全ての企業がSDGsへの貢献を標榜する中、立地地域の活性化に資する資源循環システムを、企業が主体的に構築する活動を推進。
活動上の留意事項は以下の3点
1.新たなしくみの障害となる個々のステークホルダー/関係者の困り事をイノベーションへの課題と捉え、異分野の専門家の知見を融合することで解決策を創出
2.地元自治体との連携を密にし、府県、省庁への報告と対話を通じて、主要な政策(例えば脱炭素先行地域、緑の食料システム戦略など)と整合
3.企業内では幅広い部署の人材が兼務で参画、分野毎の専門性をプロジェクトに活用