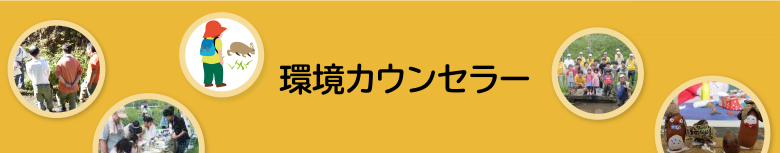| 登録年度 | 1996年度 |
|---|---|
| 氏名 | 長澤 利枝 (ナガサワ トシエ) |
| 部門 | 市民 |
| 性別 | 女 |
| 年代 | 80代 |
| 専門分野 | 廃棄物、リサイクル、環境教育、市民活動、町づくり、消費者教育、地球環境問題 |
| 主な活動地域 | 福島県南相馬市 |
| 主な経歴 | 平成8年7月より「ごみとくらしを考える市民の会」事務局長。平成10年「福島県環境アドバイザー」、平成13年福島県環境カウンセラー協会会長、平成14年福島県環境審議委員、平成21年福島県総合計画審議委員(2月任命)、平成18年南相馬市バイオマスタウン構想検討委員会長、平成20年南相馬市農林水産振興プラン検討委員 |
| 特記事項 | 平成20年度ECU理事長表彰受賞。平成20年度ECU役員改選にて執行理事に選任。 |
活動の紹介
消費生活と温暖化のつながり
日常生活と密接に関係する地球温暖化について、
検証する。日頃の生活意識が、地球温暖化を促進している。
事例・・・容器包装リサイクル法を守らないで、可燃ごみの増大によって、二酸化炭素放出を促進している。
寒暖差が激しい時節により、室内温度調節を過大に使用。
二酸化炭素の排出を促進。日常生活に必須?な自動車の使用により、二酸化炭素を過剰に排出。
このように便利な生活が、地球温暖化を促進ている。
便利な生活の見直しをする時宜である。
ごみ減量とリサイクル
行政区対象の招請。
非常に高いごみ減量とリサイクルを実践している区域。
リサイクルの実物を用意し、クイズ形式で行った。
二組に分けて、リサイクルの仕分け方、リサイクルの過程を実物と絵でく分ける方法。
20代から80代の老若男女が参加。面白いのでみんなのりのり・・・。二組どちらもゴール。
区長さんの日頃の住民への啓もうが行き届いている。
SDGsと私たちの出来ること
対象は、小学4年生30人。総合教育時間なので、予備知識があり、SDGsについては、学んでいた。
17の項目で、自分たちに身近な項目を提示し、どのような
取り組みができるのか、話し合う場面を設けた。
6.安全な水とトイレを世界中に・・・日本は6については先進国と認識。未だに汚染された水を使用する国。野外にある簡易なトイレの存在にどうしたらなくなるのかとの話し合いがされた。
13.気候変動に具体的な対策を・・・私たちが出すごみが
温暖化に繋がっていることを再認識。私たちがごみを減らす努力をすること。みんなの取り組みを確認。
14.15.の項目も色々な意見が出た。
消費生活の見直し
私たちは、日頃の生活に不自由さを感じないでいる。
便利な生活、快適な暮しにどっぷりと浸かっている。
一方で、国内産物は少なく、外国産が多くを占めている。
自給自足率が約10%。地球温暖化等により、これからの
食物等は、厳しさを増す。物を大切にする。自分で作れるものは作るなど、生活の見直しが喫緊の課題である。
SDGsと私たちのくらし
SDGsとは?についての説明。
17の項目について、持続可能な開発目標と目標達成2016年
まであと14年の認識を共有。
私たちの生活で、17目標の実践している項目の再確認。
新たに取り組む項目のうち、具体的取り組みが出来ることを事例で示す。一人一人の実践が重要であることを学ぶ。
質問に、日常生活の取り組みが如何に目標達成に繋がるかを学んだ。
SDGsと消費生活・衣食住について
⦅SDGs17の目標⦆達成まで6年を切った。私たちの生活は、残念ながらどの項目も、目標に達した・・・とは言えない。50代以降の生活者対象の講演。想定外の意見に、終活を進めている。家中にこれ程物があふれていたことに、驚いたとの意見続出。衣類・陶器・日用雑貨・捨てられない思い出の物・親から譲り受けた品物等々大変な量。
~物を大切にする世代、何時災害が起こるかわからない天変地変に備える~もっともの意見が交差した。死生観の世代には、捨てることは罪悪のなる。この両者の考えは、捨てがたい理念がある。私は、このテーマがこれ程
会場の人々に刺激を与えたことが想定外だった。
1人ひとりに生きて来た証がある。終活だから消費することは、短絡的だ。この世代の方々は消費生活・衣食住に
努力をして来た人たちといえる。ものを無駄にしていない世代と強く思った。
私は、私の理念で2年前終活をした。私の大事なものをすべて片付けた。最小限の生活用品で心地よい。だからと言って、SDGsとは思わない。その逆もまた成り立つことを知ったからだ。今回は参加者皆の討論の場になった。
野馬追と人々の暮らし
一千有余年続く国指定有形文化財「野馬追」と人々の暮らしのファイル作成。平将門から始まったと言われる馬の軍事訓練は、時を経て関東から陸奥の国に居城し、野馬追は絶えることなく、神事として今日に至っている。東日本大震災の年は、犠牲者の鎮魂として執り行った。相馬人は、
1年の暦が野馬追。人と馬の絆は強く、【人馬一体】の所以である。
ごみエコピクニック
市民参加型エコ活動「ごみエコピクニック」を2022年11月6日(日) 県立東ヶ丘公園で実施。この日は秋空に紅葉が美しく参加者は、一時の開放を堪能。市民約100人の参加。この事業は第17回目で、コロナ禍でも広い野外であること、密にならないことで実施を続けている。午前9時から10時15分まで、5コースに分かれてごみ拾い。10時30分か11時30分は、民俗芸能を披露、久しぶりの芸能を堪能。
JR繋がり支援事業を活用したが、手続きの面倒さに
大変な労力を費やしている。補助金選択を誤った。
鎌ケ谷市環境展 オンライン
コロナ禍で3年鎌ヶ谷市環境展は、ファイルを展示して頂くのみになっている。スペースも限られているので、
今回は~東日本大震災~11年目被災地の光と影~
7枚のパネル展示をお願いした。
千葉県環境カウンセラー倉田智子さんの配慮で、私のファイルの展示場所を確保して頂き感謝。
オンライン展示とのことで、私のファイルを見ることが出来た。3年前まで鎌ヶ谷市に行っていたので、現実感が
感じられない。私たちの屋内事業もコロナで中止。
そのような折に遠方からのファイル展示が出来たことで、一事業となりました。長年の連携によるものです。
東洋英和女学院一行の現場視察
2022年8月4日、「聖愛こども園」に訪問された東洋英和女学院30人の被災地現場視察を行った。
午後2時から3時30分の視察時間なので、事前に視察して頂く被災地を下見した。
当日、震災時は2~3歳だったと思われる中・高校生たち。
私のレジメを渡した有るので、現場の説明はリアルにした。震災遺構請戸小学校では、バスから下車できずに、車内での説明なので、津波の破壊力等は解せなかったようだ。その他、漁船がそのまま、自然林が破壊され、復興の名のもとに最新の工場が出来たこと等、感性に届かなかったようで、説明しながら虚しさを感じた。
「東日本大震災」は、20代以下の若者には、なかなか伝わらないと実感。まして、東京のお嬢様学校の生徒さんたちなので、距離感を感じた。
若い世代にどう伝えて行ったら良いのか。課題が残った
自立研修所での園芸活動
自立研修所に月曜日と金曜日にボランティアで行っている。研修所内の仕事が多く、外に出て植物に触れる機会を作りたいと思っていた。「園芸チーム」を作り、花苗を育てることを提案、快諾されたので友人たちからたくさんの苗や種を頂いた。研修生は4人参加。花を育てる経験はないので、土づくりから始める。ポットに培養土を入れ、頂いた花苗を丁寧に入れる。こうしてポットに入れた苗は、良く成長し花芽を付けた。8月になると育ちがよく、沢山の鉢は花が咲き揃った。
9月、研修生たちと花苗を売ることにした。
行政関係や、知人、友人にチラシを配布。良く売れた。
11月も販売。自分で育てた寄せ植えが売れることを知った。翌年も沢山の寄せ植えを作った。SDGs3.5に繋がった。身近なことでも、自然との共生、すべての人に健康と福祉、障害のある人もみんなで住みよいまちづくりが出来ることを体験した。
「東日本大震災」11年被災地巡礼視察
「東日本大震災」から1年目の3月11日、「被災地巡礼視察」として、富岡町・大熊町・双葉町・浪江町・耳相馬市を取材した。11年を経た各市町村は、国主導「イノベーション・コースト構想」と、ハード復興で変化を遂げている。浪江町「水素工場」「浪江町棚塩工業団地」はすでに稼働。一方で浪江漁港は水揚げで賑わうが、請戸町だった
広範囲は危険区域で住むことは出来ない。このように各市町村は、復興と更地になった住居後が際立つ。
大熊町、双葉町はコンパクトシティとして、住民帰還の準備を進めている。しかし、避難先での生活が定着した住民は戻らない。200人から300人である。
浪江町は、復興が早く役場周辺に集客する道の駅などにより、住民1.000人が戻る。
一方、未だに帰還困難区域があり、朽ちた屋敷、木立に覆われた田圃が点在する。立ち入り禁止の看板が至る所に建つ。この状況は、まさに被災地の「光と影」だ。
私たちは、午後2時40分に南相馬市萱浜地区慰霊塔前に到着した。午後2時46分 ご家族と黙とう。
遺族の一人が~年月が経つにつれ、ここに来る家族がすくなくなっていくな~と言う。わたくしも11年来ているが、年々少なくなっているのを感じた。
ここ北萱浜は、津波で68人亡くなった。居住危険区域になり、住民はそれぞれの選択で避難した。
跡地は「ロボットテストフィールド」「復興工業団地」
として、すでに稼働。3.11前は何代も続いて開墾した田圃が広がり、屋敷林に囲まれた大きな家が並んでいた。
かつての風景は、21世紀を象徴するサイエンスの場になった。
この萱浜地区でも、被災地の「光と影」を視た。
市民参加型『ごみエコピクニック』
震災後中止の事業。一昨年、事業復活の声が上がり、再開した。
県立東ヶ丘公園近隣住民の要望でもあった。毎回参加する人たちは、ごみ拾いのルートも良く知っている。今年はコロナ禍で、中止も検討したが、自粛生活をしている住民は、開放感を望む。コロナ対策をし、ごみ拾いルートも、5班に分かれ密を避けた。食事はパンと飲み物。1時間で解散とした。家族連れも多く、75人参加。
2012年から2022年『仲間たちと続けた再生事業』
震災から10年。仲間たちと復興再生事業を実施して来た記録誌を作成することに至った。様々な困難を経て、毎年地域の状況に沿った事業企画を実践。県内外からのボランティアの皆さんの協力で、毎回盛況。
被災地に住むカウンセラーとして、大切な歳月を資料を基に記録誌に着手。4カ月かけて完成に至った。貴重な記録誌となった。
『環境と福祉の共有』障がい者も健常者も地域で共に・・・
『環境と福祉』との連携を約30年間続けて来た。SDGsの取り組みとして、研修生たちと花作り作業に取り組む。花苗は寄贈された。土づくり、挿し芽をする。苗は移植し、育った苗を寄せ植えづくりに仕上げる。
外の作業は、心身を癒し、好んで仕事をする。8月、販売する。口コミで
購入者が増え、まずは第一歩を踏み出した。
生活環境を守るために私たちの出来ること
今年は、8月震度5弱地震。9月台風で洪水の被害を被った。異常気象は続き、農作物へ影響が出た。この要因は、「時u温暖化」による。二酸化炭素排出の減少は、大国の取り組みに拠るが、私たちの生活環境もその要因の一つである。省エネ推進も、なかなかはかどらない。身近な環境の転換を地域で取り組むことが喫緊である。
環境創造シンポジュウムパネルディスカッション
パネラー ①地元郡山市女子高校生2人 ナラティブスコラを学び、正しい情報発信実施。②福島大学環境放射能研究所准教授、海洋環境の専門家 ③被災地に住む環境カウンセラー 震災10年を取材。④「あったかふくしま観光交流大使」なすびさん。オンラインでの開催。各自の取り組みについて発言。ファシリテーターの質問に答える形式。各自の視点が異なるので、パネリストとのやり取りは皆無。発表会の感がぬぐえない。
「ごみ・エコピクニック」

コロナ下での実施理由 30年継続事業 市民周知の事業 コロナで総菜、テイクアウトごみ増加 これらの理由で事業を実施。生活様式を徹底し、グループ分けの配慮をした。約80人の参加。
「東日本大震災 9年の経過」記録誌発行日2020年12月20日
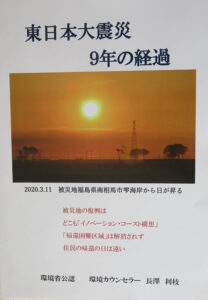
震災から9年目の今年は、「震災9年鎮魂巡礼」として取材。被災地の復興は、どこも「イノベーション・コースト構想」「帰還困難区域」は解消されず、住民の帰還の日は遠い。
8年間、被災地の環境カウンセラーとして年2回記録誌を作成続けた。被災地の現状を伝えたいとの強い思いでからである。取材を続けるが、復興はまだ遠しである。
「震災から9年 失った自然と人々の暮らしの未来は~」事業開始から10年の今回は、それそれの活動から自然・人・暮らしをキーワードとして地域のこれからを一緒に考える機会とする。

1.震災前の南相馬市 温暖な気候によって、農業・漁協・林業が盛んだ。人々の暮らしは豊かかな自然と共生していた。
2.『東日本大震災』すべて壊滅。自然と暮らしの営みは失った。
3.震災9年 自然の再生と人々の暮らしの未来志向
被災地に住む9人を取材。震災で生活基盤を失った。ようやく次世代に繋ぐ気力を取り戻す。形になり始めたのは震災から7年。自然と向き合える未来に至った。
自然と暮らしの営みの未来が開け始めた
2019年度活動実勢報告提出済
2019年度活動実勢報告提出済
2018年度活動実勢報告提出済
2018年度活動実勢報告提出済