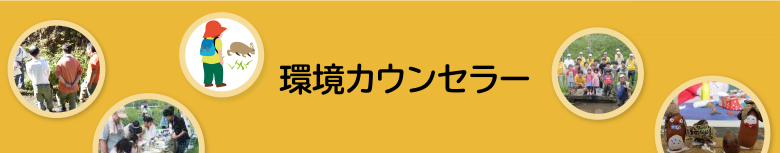| 登録年度 | 1997年度 |
|---|---|
| 氏名 | 坂部 孝夫 (サカベ タカオ) |
| 部門 | 事業者 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 70代 |
| 専門分野 | 生態系・生物多様性、地質、3R |
| 主な活動地域 | 愛知県安城市 |
| 主な経歴 | 静岡大学大学院修了、平成19年3月に愛知県環境部環境調査センター所長を最後に定年退職し、現在主に中小企業を対象に環境コンサルタント業を経営している。また、大同大学客員教授及び愛知淑徳大学、愛知工業大学非常勤講師として、環境影響評価、環境関連法規、環境教育の講義を受け持っている。 |
| 特記事項 | 資格:技術士(環境、建設、総合技術監理)、1級ビオトープ計画管理士、行政書士、大同大学工学部都市環境デザイン学科及び名城大学理工学部環境創造学科の外部評価委員 |
活動の紹介
廃棄物処理法の講演
産業廃棄物中間処理業の従業員のための社内研修の実施を提案し、私が講師として「廃棄物処理法の基本」を教授した。特に質問時間を多くして、現場の悩みを聞き取り整理し、社長に進言した。
草木のリサイクル工場指導
草木のリサイクル工場の視察と指導を実施した。搬入される草木はホコリが多く、搬入は夏場に多く、夜間操業も実施している。このため、集塵機の設置指導、騒音対策の指導を行った。
リサイクル工場の適正処理
プラスチックのリサイクル工場の指導をした。ペットボトルなどが場内に散乱していることから、まず、工場内をきれいにすることから指導した。また、目に付くところに「整理整頓」の看板の設置を指導した。
土壌汚染対策
瓦釉薬製造業の廃止に伴う工場跡地の有害物質の土壌汚染について指導した。基本は現地無害化であることを指導し、跡地にはマンションを建設する計画があることから、覆土も実施するよう指導した。
メッキ工場の現地指導
名古屋市内のメッキ工場の工場内環境施設の設置状況の指導をした。調査では、有害物質の管理が悪く、物が床面に散乱しているケースも見られたので、5S運動を指導し、社員のモチベーション向上の必要性も指導した。
現場社員への環境教育
社員教育を定期的に実施している事業者に対し、環境カ環境カウンセラーとして環境に関する研修をしたいと申出た。労働安全に関する従業員研修の後の50分間時間を頂き、リサイクル、サーキュラーエコノミーなどの説明をパワーポイントを使い実施した。
従業員からは初めて聞く言葉(専門用語)に戸惑いを見せたが、最後まで聴講していただいた。
産業廃棄物最終処分場建設指導
産業廃棄物はリサイクル・資源化を行っていくことが必須である。今回計画している最終処分場は管理型処分場であり、多種類の産業廃棄物を受け入れる計画となっていた。このため、受け入れる時点でリサイクル可能な廃棄物の分別が可能な中間処理施設を併設することを指導した。
これにより、収益は下がるが、地域住民からの信頼が今以上に高まると説明・指導した。
土壌汚染対策
土壌汚染のある廃止された工場跡地の土壌汚染対策指導は、その責任の所在が不明確であるため困難が伴う。土地所有者は往々にして有害物質のない土地として売却したいため、汚染土壌の移動を考える。しかし、汚染の拡散につながるため常に「現地無害化」を指導している。本件では、汚染された土壌を売却しようとしていたので、土壌汚染対策法の基本的な考えを示し、「汚染土壌移動の禁止」や「現地無害化」を指導した。
有害物質を取り扱う企業への指導
メッキ工場の4S運動の指導に合わせて、サーキュラーエコノミーの考え方を伝授した。出来るだけ環境負荷を与えない操業形態、薬品の最少使用方法の指導、発生した排水処理汚泥の山元還元、室内照明のLED化等、工場内をこまめに調査し、現場職員と総務担当を前に直接指導を行う。
企業の事業展開について
産業廃棄物処理中間処理業者に対し、今後は地球温暖化防止、リサイクル推進の観点から有機質肥料の重要性、並びに草木(剪定枝)などのバイオエネルギーへの活用が求められる時代になると説明した。そして、①焼却処分していた有機性廃棄物の活用などを指導し、②環境省、農林水産省などの資料集めを行い、その企業にこれらを提供した。
メッキ工場の騒音苦情に関する指導
メッキ工場の騒音指導を行った。地域の住民の代表者である町内会長から、騒音がある、という苦情があり、相談に来た。現地を調べると、隣地に4階建ての倉庫が建設されたばかりであり、その時期を境に苦情が発生したことから、この倉庫の壁からの反射音であることが解った。音の発生源は、近くの国道、倉庫の屋根に設置されていた換気扇、遠くは大型貨物船からの低周波音などであり、メッキ工場が原因者でないことを説明した。
陶器瓦の釉薬製造工場跡地の土壌汚染対策指導
陶器瓦の材料である釉薬は、瓦製造会社が釉薬会社へ調合も含めて釉薬の注文をする仕組みである。そのため、様々な色の釉薬を製造していた結果、様々な有害物質の土壌・地下水汚染が発生している。また、隣地には河川が流れており、伏流水で汚染が広がっている。
この様な状況で、土壌汚染対策のうち、現地不溶化を指導するとともに、伏流水の流入を遮断する方策も提案した。
廃棄物処理法に関する社内研修会講師
企業内研修会で廃棄物処理法のリスキリング研修をした。対象者が現場作業員であったことから、より現実的な質問があり、十分効果がある研修であった。中でも、マニフェストの目的とその使用方法、罰則についての重点説明では質問が多く出た。
介護施設のビオトープと菜園作り指導
介護施設から、被介護人のメンタルについて、環境に親しむ工夫を検討してもらえないかと相談があった。近くの農園を借りることが出来たので、みかんの苗木植え、簡単な菜園作り、ビオトープの設置を指導し、実践した。
また、水場の設置についても指導した。
有機質肥料製造工場の悪臭対策
食品残さを主原料とする有機質肥料の製造工場を指導した。近年、有機栽培への高い関心、化学肥料の高騰などから需要が伸びている。このため、生産量が増え、工場からの悪臭問題を解決するための各種方策を指導した。
現状、熟成日数が足りない。悪臭の工場外への漏れがあるなど、改善する点が多くあり、指示をした。
中小企業への社員研修実施
中小企業の社員研修の講師を務める。狭い意味の環境問題だけでなく、地球規模の環境問題、SDGs、ウエルビーイング、男女雇用機会均等法等も交えて研修を行う。
土壌汚染対策の具体的指導
工場跡地を整備し、住宅開発を行う計画の土壌汚染対策の指導を行う。自然由来のフッ素が面的に広がっている土地での対応として、不溶化埋め戻しの手法を指導する。
環境影響評価の実施計画と住民対応
産業廃棄物リサイクル工場建設に伴う生活環境影響調査の実施計画の作成と現地調査の立ち会い、調査書の作成・検討を行う。特に住民が最も関心のある騒音について測定場所の選定を事前に住民に知らせた。
有機質肥料の製造工場の環境指導
食品残さを主原料とする、有機質肥料の製造工場を指導した。近年、有機栽培への高い関心、化学肥料の高騰などから需要が伸びている。このため、生産量が増え、工場からの悪臭問題を解決するための各種方策を指導した。
メッキの試験に関する法的内容指導
メッキ企業が公共の工業指導所へ小型メッキ設備を持ち込み試験を実施する場合の水質汚濁防止法、廃棄物処理法に係る届出等の法的課題について指導を行う。試験は6ヶ月程度であるが届出を行ない、責任者を明確にするよう指導した。
豊田市事例研究勉強会
豊田市は公害防止協定を締結している市内の企業30数社を対象に講演とワークショップを計画した。そのファシリテータとして依頼があったので対応した。それぞれの課題をもちってグループワークを行い、発表し。私が講評することとなった。
中国天津市主催土壌汚染対策フォーラム
中国天津市は三重県四日市市と姉妹年提携している。今回天津市において、土壌汚染対策法が施行されたので、専門家の講演を聴きたいという要請に基づき、日本における土壌汚染対策事例を講演した。
中国からは、国の研究機関、企業と大学生、合計約100人の参加であった。フォーラムは2日間実施された。
天津では、5月から法が施行されたばかりで今後どのような方向へ向けて対策をしていくのか検討中であった。
鉛再生工場の環境への負荷低減指導
鉛再生企業は外国産の鉛インゴットの低価格化により、経営が苦しい状況にある。つい環境対策への投資がおろそかになる傾向がある。このため、工場を視察し、原料や製品置場の整理整頓、必要以上の原料を持ち込まない、製品の早期搬出など工場内の整備を指導した。また、土壌汚染につながらないよう社員教育を徹底するなど、3S運動、5S運動、報告・連絡・相談(報連相)運動の徹底を指導し、環境に負荷をかけない工場運営を構築っすることを応援した。
水質汚濁防止法の概要
企業からの依頼により、新入社員に対して、環境カウンセラーの見地から水質汚濁防止法の概要をお話してほしいとの依頼のより実施した。対象者の専門分野は文系、理系と入り交ざっており、講師としての難しさを実感した。
碧南市・碧南商工会議所の環境貢献表彰の企画
碧南市と碧南商工会議所が28年度に表彰制度を創設することとなった。そのための環境分野の表彰の目的、対象者(企業・学校・NPOなど)など様々な点で細かにアドバイスをする。