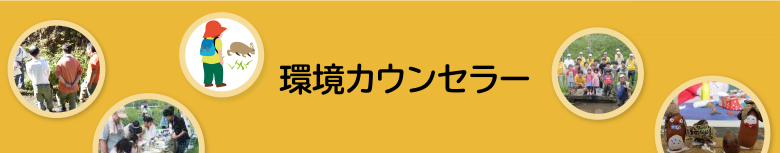| 登録年度 | 1997年度 |
|---|---|
| 氏名 | 須藤 邦彦 (スドウ クニヒコ) |
| 部門 | 事業者 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 80代 |
| 専門分野 | 地球温暖化、資源・エネルギー、3R |
| 主な活動地域 | 兵庫県神戸市 |
| 主な経歴 | 川崎重工業(株)神戸本社に在職中は全社の環境管理統括補佐業務を担当。その間自社所有の産業廃棄物処理センター、最終処分地の管理・運営をも担当。現在は中小事業者等向けにEMSに関するコンサルタント・審査等を実施中。 |
| 特記事項 | 環境カウンセラー(事業者・市民)、公害防止管理者、EA21審査人、KEMS主幹審査員、ISO14001審査員補、地球温暖化防止活動推進員ほか。神戸市地球環境市民会議委員ほか。 |
活動の紹介
PFASとはなにか?その性質と事例を知る
PFAS(有機フッ素化合物)はアルキル基の全てのHをF原子に置き換えた基で撥水性、耐熱性、対向性がある自然界には存在しない物質です。撥水撥油コーティング剤、泡消火剤、航空機用油の抗腐食剤、加工補助剤等に使用され、最終的に安定なPFASになり環境中に残留する。各地で地下水や土壌汚染が発覚し、汚染された飲料水の人への健康影響(血中濃度の増加)が懸念されている。水道水の安全確保が第一で水質基準は強化されたが、PFASの一部は製造されており、発生源対策の徹底、活性炭による除去対策、PFASを含む食品・日用品の利用回避等の対策が必要となる。
環境カウンセラーの役割と資質
環境カウンセラー登録後多くの企業(特に中小企業)様からのご相談を受けてきました経験と実績を踏まえ、レビューの意味を含めて今回本講座を受講しました。特にカウンセラーに求められるものを主としてよくまとめられており、各項目ごとの説明に納得しながら拝聴出来ました。特に「あること」について、それがあることとして成立している理由について一つの物語として語れることは大きな武器になる事、またインターネットメディアの偽情報等への対応とクリティカルシンキング及び生成AIに興味を覚えた。
気候の危機にどう向き合うか
昨年世界で記録的な高温(産業革命前+1.6℃)が紹介された。気温変化シミュレーションによればGHG排出量が低い場合は2℃で安定だが、高い場合は+5℃位になる可能性もある。温暖化が進むと影響が深刻化し、特に原因に責任のない人達が深刻な影響を受けることになる。緩和策と適応策で対応するも現状の排出削減ペースでは不十分となっている。日本は略約束通り推移しているが、国民のできることは「我慢」ではなく、関心がない人も参画できるシステムを構築することであり、そのためには「規制」も一つの方法である。人類は化石燃料文明を卒業しようとしている。
環境教育・ESDの最新動向等について
昨年環境教育等促進法で基本的方針の変更があり、持続可能社会への変革に向け環境保全活動、環境教育、共同的取組の方向性を提示。具体策として環境教育の一層の推進、中間支援機能活用の取組、体験機会の場の積極的活用、若者の社会変革への参画、基本方針達成状況の検証等がある。地球の環境収容力を越えつつある3つの危機(気候変動、生物多様性損失、排水汚染)を踏まえ、経済・社会的課題を熟知し、目指すべき文明・経済社会の在り方として目的を「Well-being(高い生活の質)」に置きこれを目指した「新たな成長」(市場価値+非市場価の向上)を実現する提言があった。
「海と生き物たちの未来」について
温暖化対策を目的に神戸市民及び温暖化防止活動推進員を対象に「垂水連絡会」主催の首題の環境セミナーを垂水水産会館で実施した。内容は気候変動(温暖化)による極端現象の発生、平均CO2濃度の増加、魚たちの異変、全国的な漁獲量減少等の現状説明があった。特にイカナゴ、サンマ、スルメイカの漁獲量減少が顕著で、理由は遠洋漁業の減少、産卵場の水温上昇、外国船の影響等のようだ。他方世界的視点では海面漁獲量は世界の漸増に対し日本は1985年頃を境に減少し、イカナゴ漁獲量では日本が不漁続きに対しノルウェイは大幅増加を辿っている現状報告があった。
研修2;基礎自治体の環境施策
基礎自治体の定義・役割責務と伊勢崎市の環境施策と取組を受講。本市の特色は多くの幹線道路と河川が通る交通の要所で自家用車所有数が1.7台/家族、65ヶ国の外国人が居住し人口21万人中の7%を占めている。森林はないが河川、沼そして公園が多いことを踏まえて、「いせさきGX]を掲げ取り組もうとされている。環境問題の解決には脱炭素社会の実現のみではなく、市の進める全ての施策や事業でも「環境配慮」が盛り込まれた成果となっているようにしていきたい。
研修2:脱炭素社会づくりを戦略的に考える
リオの世界サミット以降共通認識となった「経済成長と環境保護の両立」の観念を更に発展させてSDGsの目標をも配慮して、茅恒等式を個人単位の家庭部門の対策に取り込まれ、特に生活満足度(快適性)のファクターを盛り込み展開されたのがユニークな試みであった。
環境施策及び環境教育・ESDの動向について
環境省から「最近の環境施策の動向」及び「環境教育・ESDの動向」を受講した。WMO報告は2023年で既に1.45℃となり、パリ協定の目標達成が困難の警鐘を発した。日本は、この10年間の地球環境への対応が数千年先まで影響を及ぼすので「世界気候行動サミット」で全ての国が共通目標「ネット・ゼロ」に向けて取り組むことを訴えた。具体的には持続可能な社会経済システムへの転換、炭素中立・循環経済・自然再興の同時達成、GXと地域の脱炭素化実現、共同で運営するESD推進ネットワークを通しESDの活動を推進することなどである。
日経SDGs/ESG会議「サステナビリティ経営と企業価値向上を実現する日本型人的資本経営とは」
不確実性の高まる環境下で社会及び企業の持続可能性を重視した経営が課題である。日本では①周囲の人を助け合う②組織所属愛が強い③長期間雇用といった良い組織土壌が既に存在しており、欧米型経営に対応する人材育成の妥当性が問われるが、日本型人的資本経営(最重要戦略)は企業にとって「あるべき人材像」を作る事である。経営戦略、時代背景、パーパス・経営理念等の広い視野で定義し、意識改革・制度改革・行動改革により実現を図る。所謂「人材の変革」が重要である。
日経SDGs/ESG会議「SXと人的資本を経営の主軸に」
講演に参加し自己研鑽を実施。内容は盛沢山。有意義でその一部を紹介する。企業は短期的でなく長期的な持続可能性を重視し,ビジネスの安定だけでなくESGを両立する経営に変革していく必要がある。三位一体のガバナンス改革と人的資本の価値創造が重要となる。資本生産性の向上、投資家との対話を通じた企業価値の創造、ESG,SDGs推進による持続可能な中長期計画の実行と共に、持続可能性の担い手となる人材は管理対象の人的資源ではなく価値の創造増殖を見込める人的資本が対象となる。
令和4年度環境カウンセラー研修2講演「再生可能エネルギーと地域再生」
2050年カーボンニュートラル実現に向けたエネルギーの脱炭素化対策として①自らのエネルギー使用量の把握と透明化②省エネの可能性追求③使用電力の再エネ化率の引上げ④化石燃料使用の場合はCO2排出量のより少ない燃料に転換、具体的実現策として住民等需要者側の合意に向けた仕組み、方策、関連団体と一体となった連携体制、及び地方公共団体の強いリーダーシップのもと、地域経済の循環や住民の暮らしの質の向上に繋がる取組が要求される。
令和4年度環境カウンセラー研修主催者講演「今、なぜ『サステナブル』なのか」
①地球の環境容量の限界とSDGsへの対応の必要性
②「気候危機」と「コロナ禍」への同時対応
③感染症発生と生物多様性の損壊
④ウクライナ戦争による経済社会システムへの影響
⑤社会変革のためになすべき3つのアプローチ
・脱炭素家への挑戦、・循環経済への移行、・分散型・自然共生の形成
地球と共生・環境の集い2022
(公財)ひょうご
環境創造協会設立50周年を記念して講演「気候危機のリスクと社会の大転換」及び記念講演「県環境行政とあゆむ50年と目指す未来」を自己研修と共に活動しているメンバーとの親睦を兼ねて受講した。