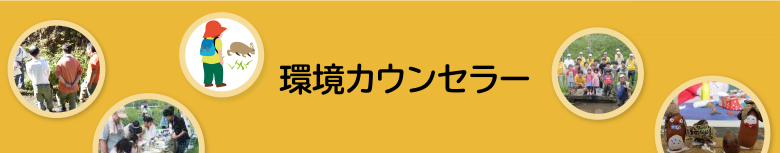| 登録年度 | 2003年度 |
|---|---|
| 氏名 | 村田 明 (ムラタ アキラ) |
| 部門 | 事業者 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 70代 |
| 専門分野 | 資源・エネルギー、公害・化学物質、3R |
| 主な活動地域 | 大阪府河内長野市 |
| 主な経歴 | 総合化学メーカーで研究、製造部門を経て、環境保全の業務に従事。事業所の環境管理計画を策定・実施する中で、とりわけエネルギー管理や化学物質のリスク評価、およびリスクコミュニケーションに取り組んできた。またマテリアルフローコスト会計(MFCA)の導入にも取り組んだ。 |
| 特記事項 | 公害防止管理者や衛生工学衛生管理者などの環境関係の資格を取得。14年間JICAによる大気汚染対策研修コースの講師を担当した。現在、物流関係を中心に環境保全に関する啓蒙活動を行っている。 |
活動の紹介
物流施設設置に関する支援
物流施設の保管設備の設置に関する、諸届け出及び設計・建設に関して支援を行った。特に消防法の危険物施設に関する施設であったことから、保管品の安全管理を重点的に検討した。準備期間を含め、実活動は10か月。
ISOマネジメントシステムの有効性の改善
ISOマネジメントシステムでは、導入時には文書管理や記録管理に着目した内容が強調されるが、本管理システムが英国の管理標準をベースにしており、従業員の多様化にこそ即したシステムであることを説明し、従業員の目標管理や教育に関する項目を見直し、充実させた。準備期間は、約3か月を要した。
マネジメントシステムにおける予防処置のデータベース化
ISOマネジメントシステムを導入している依頼先に対して、不具合が発生する前に実施する予防処置の重要性を説明するとともに、実施した予防処置をオンライン化及びデータベース化し、その内容解析についても検討した。準備期間には、ほぼ2か月を要した。
ISOマネジメントシステムの改善
委託元事業所のISOマネジメントシステムの業務の効率化と確実性を高めるため、文書管理のオンライン化を推進した。準備期間は約1か月。
文書管理は、ISOマネジメントシステムにおいて重要な事項であるが、委託会社では、その業務と維持管理に相当の作業負荷がかかっていた。
既存の文書、記録様式類をできる限りイントラ及び共通ホルダーに掲載管理することとし、紙で扱う文書類の数を徹底的に削減した。現在、特に問題なく運用されている。
物流業界紙への投稿
物流業界紙からの依頼で、物流事故防止のための業界紙への投稿を行った。原稿作成期間は1日。製造業の事故率を下げるための管理基準を物流業界に紹介し、反映させることにより、物流事故の削減を図り、事故に伴う環境汚染の回避などを含む内容であった。他業種の管理方法を学ぶことにより新たな管理方法が見えてくることを確認した。
リスク評価方法の構築と教育
委託元における企業リスクを低減させる目的でリスクの評価方法と対策の実施基準を定めた。準備期間は教育も含め約1か月であった。委託元の環境、品質、安全、コンプライアンス等に係る潜在的なリスク要因について、加点法によるリスクレベルを決定し、ランク分けする手順を策定した。さらにそのランクに応じた対策の基準をガイドラインとして作成し、従業員教育を経て実施するに至った。当初は上記内容を目的としていたが、これにより対策実施の優先順位の決定にも参考となるなど予想以上の結果となったと感じている。
ISOマネジメントシステムにおける予防処置のオンライン化
委託元企業におけるISOマネジメントシステムの業務効率化の一環として予防処置に関する運用をオンラインで行うこととした。準備期間は約1カ月であった。ISOマネジメントシステムにおいて、潜在的な不具合を是正するために予防処置を行う事が求められているが、その実施を促すためオンラインで運用できるようシステムを作成した。変更管理に関する内容も含め、一元管理できるシステムとして稼働中である。
ISOマネジメントシステム教育
依頼元(企業)の新入社員教育の一環として「ISOマネジメントシステムの導入教育」を行った。
目標設定と実績管理(進捗管理)の厳密化
ISOに基づくマネジメントシステムの運用について、目標に対する実績の進捗状況を見える化し、運用の厳密化を行った
廃棄物処理の法的な適合性と効果的な方法について指導
産業廃棄物の収集運搬業者について、電子マニュフェストの運用について確認指導を行った。また産業廃棄物発生事業者について、法8条の自治体への報告業務について指導した。
施設設置に関する法的手続きの確認
物流会社において新倉庫建設に伴う法的な手続きや必要な施設対応について指導した。関係法令は、消防・建築関係のみならず環境関連法令として土壌汚染対策法、大阪府条例(炭化水素・緑地規制)等である。
施設設置に関する環境負荷の試算実施
物流会社において新倉庫建設に伴う低温空調設備の消費エネルギーの試算、発生廃棄物の量とその処理方法、及び保安防災に関するリスク対応等を指導した。
廃プラスチック類の管理
廃プラスチック類の海洋汚染を防止するため、企業内の廃プラスチック類の回収・保管処理方法について手順を定め、文書化し教育した。また、保管プラスチック製品の取り扱い不具合による飛散・拡散防止などについても同様に手順を定めた。
マネジメントシステムの定着化に関する指導
ISO14001環境マネジメントシステムをはじめ、ISOに基づくマネジメントシステムの認証を取得している組織は多くあるが、認証取得後10数年を経て、活動の形骸化や若手担当者の育成などの課題を抱えている場合がある。これらの運用について規格本来のあるべき姿となるよう日常の活動内容から指導し、システム運用の改善を図った。
環境安全ニュースの発行
委託先会社の社内啓蒙のための教育紙を定期的(月刊)で発行した。環境関係のみならず、安全・品質の内容もおりこみ、啓蒙資料を作成した。
低温設備のエネルギー消費に関する指導
大型物流低温倉庫の設置に際して、エネルギー消費量の試算を行い、設計施工段階で参画した。とりわけ、昨今の気候変動を見据えた対応についても検討し、依頼先に対して指導を行った。
物流倉庫保管品の安全性評価
新規物流倉庫の設置にあたり、保管製品について環境や人体への影響、及び保安防災上の安全対策等について企画し、事前評価するとともに社内教育を行った。