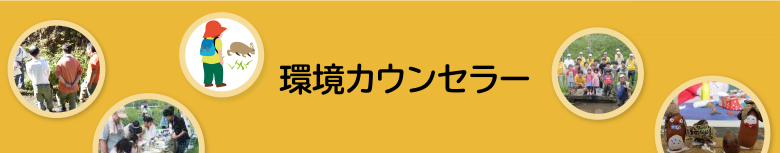| 登録年度 | 2013年度 |
|---|---|
| 氏名 | 高山 博好 (タカヤマ ヒロヨシ) |
| 部門 | 市民 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 60代 |
| 専門分野 | 生命、自然への愛着、生態系・生物多様性 |
| 主な活動地域 | 愛知県刈谷市 |
| 主な経歴 | 水族館飼育員していてもっと直接的に多くの人に自然の事、生物の事を伝えたくなり、誌紙面への掲載をするようになった事から環境学習の支援をする機会が増えてきた。また、自ら主催する田んぼの学校を通じて、生物を増やし、参加者が生き物に触れ合える環境を提供してきた。 |
| 特記事項 | ─ |
活動の紹介
油ヶ淵フィールドワーク

学区内には県内唯一の天然湖沼があり、その歴史や民話などを調べてきた上で、自然についても知る観察会にした。晩秋に生きものを見つけるのは難しいかと思ったが、児童たちのたくさんの目でフィールドサインなどを含めて見つけることができた。座学では汽水湖という特徴があること、湖岸にヨシが茂っていることなどを話した。
地域の自然観察とホタルの保全

校内には「ビオトープ」と呼ばれるホタルの飼育施設があるが、コロナ禍で活動が中断されてしまった。「体験農地」と呼んで、休耕田を借りて湿地と畑にしている。学区内にはホタルの舞う川があるがその数は減少している。その3箇所の自然観察をしながら、児童たちに地域の自然はどのような特徴があるか、もっとよくできるか考えてもらった。ホタルが生息するのに必要な環境などの講義も行なった。
田んぼの生きもの観察

学校に接した公園に田畑があり、それを利用して田んぼの生きもの観察をした。しかし、学校の都合で中干し後の観察会となった。先生と相談して、私も児童も事前に水の入った状態で観察をしておいて、中干し中と生きものを比較することにした。最も身近な生きものの生息空間である田んぼ、里山の生きもの環境を考える機会にしたつもりだが、児童の思いは地球環境に発展して調べ学習していた。
学校ビオトープの生きもの探し

校内に作られたビオトープ(陸地・水辺)での生きもの探しを通じて、今後どんなビオトープになったらいいか考えてもらった。メダカなどは減り、アメリカザリガニは増えている。子どもたちなりに、どうしたら増えてほしい生きものが増えてくれるかを考え、実践までしてもらった。流れに水草があると魚が泳ぎにくい、草が生えていると自分らが歩きにくいと徹底した草刈りをしてしまった。
学校林の生きもの調べ

中山間地の小学校で校内外は自然にあふれているけれども、授業で使うことはない。環境学習の時間を使って、生きもの調査をした。小さな生きものから、目にすることはできなかったがフィールドサイン等で大型哺乳類までが過ごしているようだ。ホトケドジョウなど絶滅危惧種など珍しいものを見つた一方で、思ったより多くの種類を見つけることができなかった。通学路沿いと森の中と比較して、環境と生き物の関係を感じてもらった。
森前川を通じて自然との共存を考える

通学路に面して流れる川だが、柵が巡らせてあり、普段は興味を持つことが少ない。どんな生き物がいて、現状の皮の様子を知り、今後どんなかわになったらいいかを考えた。
ビオトープの生き物観察

地元の高齢者に協力してもらって作ったビオトープであるが、外来種の展示場的な環境が出来上がっている。ビオトープを作ったら、すぐにそこで生き物が見られるようにしたい気持ちはわかるが、身近に多い外来種を話してしまった結果である。
生き物観察した後に、「ビオトープとは何か?」からお話しして、どんなビオトープにしていきたいかを事後学習した。その成果は授業参観で発表した。
学校林の土の中の生き物観察

学校に隣接しているが校門の外であるために、授業や放課に利用する機会がない学校林を、森の土を作る生き物の視点から生態系を見つめてみた。小さな生き物を虫眼鏡や顕微鏡で観察し、その多様性に気づいてもらった。
その後の事後学習では、もっと広い視点で生態系を見つめ、地球環境まで関心を広めた。
ビオトープの生き物観察

校内にビオトープがあるがなかなか利用されていないので、どんな生き物がいるか調査をして、どんな生き物のいるビオトープになってほしいか考える機会とした。捕まえた生き物の名前や在来種か外来種かを調べた。
クラス内で関心のあるテーマごとにグループを作り、調査後に調べ学習をした上で、どんなビオトープになったらいいかを話し合った。在来種の棲みやすい巣を作ったり、外来種の駆除など子どもたちなりに考え、授業参観の日に発表した。
メンマを作りながら竹害問題を考える

足を踏み入れることが困難な竹藪が増えている。竹が溢れる一方で筍すら輸入品が増えていて、環境にも食品問題にも関心が薄れている。
実際に足を運び、筍を収穫し、加工することで、竹林問題を考える機会を与え、ゴールデンウィークに開催することでレジャー感覚で取り組んでもらった。
中華料理屋さんにも協力してもらい、メンマの加工の仕方を学んだ。
保育園での自然体感企画
保育園での自然体験授業の開催について、これまで7回にわたって打合せの機会を設けてもらった。企業が社員離職対策として設置した、保育時間の長さを売りにしている無認可保育園であり、認可保育園に比べて自然体験が極端に少ないための対応策を相談された。園内にバタフライガーデンなどや田畑を設けて、植物そのものの栽培や観察に留まらず、食育に結びつけること、訪れる昆虫の観察を勧めた。また遠足では、芋掘りなどの農業体験などを盛り込むように進言している。
環境審議会
市の環境政策について審議委員を受託して2年間務め、策定した案についての助言をした。「外来種についてコラムなどで市民に知ってもらうような形をとったが、特定外来生物の問題の重大さをもう少し強く訴えてもよい。また、農業への政策にも関連するが、耕作放棄地や荒廃している竹林への取り組みなどへの積極的な関与すべき。環境学習の継続が重要」
総合学習 川の生きもの
学校の近くを流れる川の中に入って、実際に生きものを採集した。五感で感じられる水質検査を行い、採れた生物種や川の様子に着目してもらった。気に入った生きもの1種をスケッチする時間を設け、じっくり観察するように仕向けた。川の空中写真を見てもらったり、指標生物の話をして川のきれいさを感じてもらった。外来種か在来種かを調べて、なぜ外来種がいるのかを考えてもらった。質問時間も設けた。
林間学校の事前学習
自然豊かな林間学校に行く前に、自然観察の仕方を事前に学習したいとのこと。主に昆虫をどう探したらいいか、見所を校内の雑木林や芝生広場、水辺ビオトープを利用して予習するつもりだったが当日が雨天のため、下見した際に撮影した昆虫写真と見つけた場所などをスライドで見てもらい、実際の山ではどのような注意や観察ポイントを探したらいいか、クイズにして答えてもらった。
総合学習 学校ビオトープの観察

校内にビオトープがあるが有効利用されていない。今まで水辺だけに注視されていたが、見所は草地や樹木、堆肥置き場なもあることを提案し、グループ分けして順番に観察の仕方を示し、実際に最終をして環境と生物の多様性を感じ取ってもらった。外来種も見られたため、在来種との関係の話もした。
NPO基礎講座 環境とNPO

環境活動をするNPOの実践例と課題について講演。コロナ禍ということもあり、会場とリモートを自由に参加者が選べる方式になっていた。
一見緑豊かに見える地域でも耕作放棄地や里山の荒廃があることを示し、障害者も含めて一般市民が担えることを解説し、NPOとしてどのようなことを実践・展開していくかを話した。
地域を流れる川の生きもの観察

毎年4年生を対象に6月頃に地域の生きもの観察をしている。今年はコロナ禍で開催時期を従来より延期して、観察は担任と児童だけで、生きもの話や子どもたちからの質問はリモートで授業をした。
環境審議会
2019年度に策定した市の総合計画に続いて環境基本計画案を審議する委員会に参加し、市民の要望や課題に応えられるよう努めた。
審議会は毎回2時間ほどで、前年から5回にわたって審議した。中学生からも事前アンケートに参加してもらえるように助言し、生態系についても環境計画に取り入れるよう助言した。SDGsの理念も加わって自然生態系の保全や環境学習の更なる推進もあり、従来から大きく前進し、中学生にもわかりやすい計画を立てることができた。
食農体験

食と環境の関わりを体感できるよう園内に設けた田畑で作物を作りながら、生きもの観察や調理などを行った。午前2時間は農作業をしながら生きもの観察、午後1時間はその都度、関心を持ったことに対して子どもたちにお話をした。