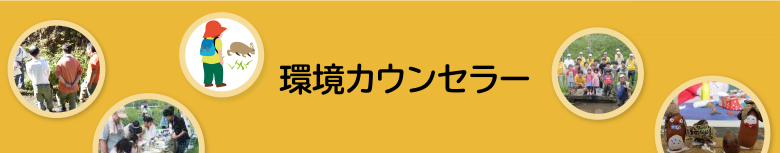| 登録年度 | 2021年度 |
|---|---|
| 氏名 | 高村 裕美 (タカムラ ユミ) |
| 部門 | 市民 |
| 性別 | 女 |
| 年代 | 40代 |
| 専門分野 | 地球温暖化、資源・エネルギー、消費生活・衣食住 |
| 主な活動地域 | 埼玉県さいたま市 |
| 主な経歴 | 公立小中学校事務職員として勤務。埼玉県環境アドバイザーとして教師・児童生徒・PTAに地球温暖化やSDGsの授業・講演を行っている。環境アドバイザーとして上尾市図書館協議会委員に就任している。地球温暖化防止活動推進員としてさいたま市地球温暖化対策地域協議会委員に就任している。 |
| 特記事項 | 彩の国環境大学実践課程修了。環境社会検定試験合格。地球温暖化防止コミュニケーター。省エネ・脱炭素エキスパート(家庭分野)。中学校一種「社会」、高校一種「地理歴史」「公民」教員免許取得。 |
| 直近の研修受講年度 | ─ |
活動の紹介
市環境審議会
市環境基本計画年次報告書(令和5年度版)に関する事項および市地球温暖化対策実行計画について審議しました。市の環境基本計画の基本目標等施策内容について、また、取組進捗状況について報告を受け、審議委員として助言しました。
SDGsと私たちの生活

12月2日(月)5年生の児童を対象にSDGsの目標12「つくる責任つかう責任」13「気候変動に具体的な対策を」14「海の豊かさを守ろう」15「陸の豊かさも守ろう」を中心に環境学習の授業をゲストティーチャーとして行いました。児童の感想としては「今まで環境についてあまり興味がなかったけれどお話を聞いて決して他人ごとではないと思えるようになった」「(自分で)ネットなどで検索しても、あまり納得できませんでしたが、今回すごく納得することができました」「生活のどんな場面で環境に影響を与えているのかがよくわかった」「たくさんのクイズがおもしろかった」「環境のことを何も知らなかったけれど、この学習を通して「今起こっている事」またそれに対する「対策」を理解することができた。今の私たちにできる最大限のことをしていこうと思った」などがありました。
生物多様性と私たちの生活

ゲストティーチャーとして10月16日(水)5年生の国語で学んだ生物多様性の学習を深める授業を行いました。児童の感想としては「いろいろなくわしい説明があってわかりやすかった」「生物多様性はすごく大切なことだとわかった」「日本は生物多様性が高い国ということにびっくりした」「日本にしかいない種類の生物もいると知っておどろいた」「生物は気持ち悪いだけだと思っていたけれど生物や自然は人にとってとてもかかせないものだと学びました」「現在はすごいスピードで絶滅していることにびっくりした」「自然環境の回復にはとても時間がかかることにおどろいた」「みんながのんでいる水は自然からできているとわかって自然を大切にしたいと思った」などがありました。
身近な自然と私たちの生活

9月11日(水)12日(木)19日(木)クラスごとにゲストティーチャーとして1年生の生活科の授業を行いました。人間の生活は自然や環境によって支えられていること、身近な虫や小さな生き物も人間にとってなくてはならない存在であることを小さな子供でも理解できるようていねいに説明しました。子供たちの感想としては「むしはすごい」「しぜんはむしとなかよくしている」「いきもののやくめがわかった」「いきものをたいせつにしたい」「はっぱもつちのえいようになるのはびっくりした」「いろんないきもののおかげでむしやしょくぶつやどうぶつやにんげんもくらしているんだなとおもった」などがありました。
自然と私たちの生活

6月27日(木)5年生を対象に林間学校の事前学習として講義「自然と私たちの生活」をしました。自然や環境問題について調べた児童のグループ発表を拝見した後、地球の大気の薄さ、樹木の光合成、人間の使える水の量などについて、また、人間活動による自然破壊、汚染、地球温暖化や海洋プラスチック、貧富の格差、人口問題などについてお話しました。児童の感想としては「初めて知ることがいっぱいでおもしろかった」「木や虫は人間にできない大事なことを行っているのがすごい」「虫がいないと人間は生きていけないとわかった」「人が使える水はあまりにも少ないと思った」「プラスチックは自然にかえらないことにびっくりした」「自然と環境を大切にすごしたい」「できることを積極的にしていきたい」「他の国の知らないだれかの問題ではなく地球全体の問題と考えるようにして行動したい」などがありました。
森林と私たちの生活(5年生 社会)

日本は世界有数の森林大国だが、化石燃料や海外産の安い木材に押され、国産の木が利用されなくなっていること、林業の担い手が減り、山が荒れていること等を伝えた。また、世界の森林について、日本の食品にも多く利用されるカカオやパーム油など身近な食材が生産されている国で、森林減少が続いていること伝えた。児童は、「クイズなどがあって楽しかった」「森林にはたくさんの役割があることを知った」「「森林(FSC)マークがついている物を買いたい」など、興味関心を持ち自分事として考え行動しようとする様子がうかがえた。
SDGsと私たちの生活(6年生 家庭科)

家庭科の課程として授業をした。環境に関連する4つ、目標12・13・14・15の中から各自興味のある目標を1つ選び、同じ目標を選んだ児童同士でグループ討議をしてもらった。ワークシートを配布して①目標を達成した社会(生活)の姿、②①の社会を実現するために日本がすべきこと自分がすべきことは何かを話し合い、代表の子に発表してもらった。児童からは「自分自身が課題を理解し、伝え、一人一人が考えて生活することが大切だ」「皆と一緒に協力して取り組みたい」等、興味を持ち自ら行動を起こしたいという積極的な意見が多かった。
市環境審議会
市環境基本計画の令和4年度(最終年度)年次報告書に関する事項、市地球温暖化対策実行計画における令和4年度(最終年度)年次実施状況の報告について審議する。
身近な自然と私たちの生活(1年生 生活)

教室にて、生活科の授業としてお話をしました。植物・虫と人間の生活(衣・食)との関わりについて説明しました。児童の感想としては「はじめてしったことがいっぱいあってたのしかった」「虫はきらいだったけど、たくさんはたらいてくれているとしって、すきになりました」「どうぶつからえいようをもらっていることをはじめてしった」「むしがいるからにんげんがいきていけるんだとおもった」「ふわふわなわたがようふくのもとになってすごかった」など興味関心をもち、身近な自然や生き物の大切さを理解できたことがうかがえました。
環境問題と私たちの生活(4年生 総合)

総合的な学習の時間の授業でお話をした。地球温暖化、森林・生物多様性の減少、ごみ・海洋プラスチックについて原因や影響を説明した。自然のしくみ(水や物質の循環)についても丁寧に話した。また、日本は海外から多くの物を輸入しているため、私たちの生活は海外の森林や生物多様性の減少にも関わっていることを伝えた。児童は「学習してわくわくした」「自然がぐるぐるまわっていて驚いた」「私たちが気づかない所で問題がおきている」「できることをどんどんやっていきたい」など自分事として捉え、行動したいという意見をくれた。
私たちの生活 昔と今
3年生(78名)を対象に、社会科見学(歴史と民族の博物館、ごみ処理場)を深める学習として、各学級1コマ(45分)の授業を行いました。10月20日(木)1時間目3年3組、3時間目3年1組、4時間目3年2組にて実施しました。児童は、「歴史と民族の博物館」で見た昔の道具や建物、ごみ処理場で見たことを思い出しながら、昔と今の暮らし方の比較をして、今の問題点について積極的に考えて発言していました。授業後の感想用紙には、「昔も今と同じようにくらしていると思っていたから驚いた」「昔の人は今よりもずっと大変なくらしをしていたとわかった」「今でも日本の昔のような生活をしている人が世界にはいるから、世界をよくするようにみんなで考えたい」「昔の人は物をとても大切にしていた。私もこれからは最後までしっかり使って物を大切にしたい」という声が多くありました。
環境問題と私たちの生活
4年生(84名)を対象に、総合科単元「みつめなおそう 私たちのくらし」の学習として、各学級1コマ(45分)の授業を行いました。10月12日(水)5時間目に4年3組、10月14日(金)5時間目4年2組、10月13日(木)4時間目4年1組にて実施しました。児童は、真剣に聞き、積極的に発言をしていました。特にクイズはとても盛り上がり、正解した児童は声をあげて喜んでいました。授業後の感想用紙には、「とてもおもしろかった。また聞きたい」「自分で調べた時にはわからなかったことも知ることができた」「知らないことがたくさんあった。少しでも地球がよくなるように、できることから取り組んでいきたい」「もっと環境問題について知りたくなった」という声が多くありました。
虫とわたしたちの生活
小学1年生(101名)を対象に、生活科単元「いきものとなかよし」の学習として、各学級1コマ(45分)の授業を行いました。10月5日(水)5時間目に1年1組、10月7日(金)3時間目1年3組、4時間目1年2組にて実施しました。児童は、虫の写真や植物の写真を見て「これ知ってるよ!」「見たことある!」と元気よく興味を持って話を聞き、積極的に発言していました。授業後の感想用紙には、「虫さんがかふんをはこんでいるとしらなかった」「虫さんがこんなにたくさんおしごとをしているとわかった」「虫はきらいだったけれど、虫にありがとうと言いたい」「虫や小さないきものをたいせつにしたいです」という声が多くありました。
SDGs研修会
SDGsの考えを広め一人一人の行動を促すために、教員(28名)を対象にプレゼン形式(約30分)にて行った。諸外国と日本の状況比較を行い、脱炭素・循環経済社会へ向けた世界的な動きを説明した。「普段は何も考えずに生活していたが、私たちの生活が環境問題へとつながっていることを再認識したので、できることから取り組んで行きたい」「こんなに大変なことになっていると思わなかった。もっと考えて子供たちにも伝えていきたい」等の感想をいただいた。
SDGsと私たちの未来
学校保健委員会の中で、PTA・教員(34名)を対象に、SDGsに関する知識を広め行動を促すことを目的に行った。約40分間、小学校の体育館(エアコン有)にてプレゼン形式で行った。地球温暖化やプラスチック問題について「地球規模で考えて足元から行動する」ことを説明したので、近くは車ではなく自転車で行くこと、賞味期限の近いものから商品を購入する等自分のできることを積極的にやっていきたい、子供にも伝えて行きたい等の感想をたくさんいただいた。