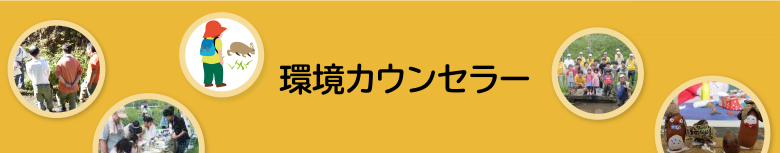| 登録年度 | 2022年度 |
|---|---|
| 氏名 | 高野 潤一 (タカノ ジュンイチ) |
| 部門 | 事業者 |
| 性別 | 男 |
| 年代 | 60代 |
| 専門分野 | 資源・エネルギー、産業、3R |
| 主な活動地域 | 大分県大分市 |
| 主な経歴 | 詫磨グループにて、環境経営の構築運用を主導し、エコアクション21の認証登録を行った。2022年からエコアクション21審査員として審査やコンサルタントを行っている。また、森林開発地の活用を提案し、森林再生、再生可能エネルギーの構築、土砂崩れや河川氾濫などの抑制を目指している |
| 特記事項 | エコアクション21審査員(登録番号200024) |
活動の紹介
残土処分地の確保と処分方法
テーマは土の処理方法を確立することです。残土の多くは建設現場から排出されます。いわゆる建設残土と言われるものです。私への相談は、水道工事で排出される土の処分方法です。大分市の水道工事件数は年間2000件程あり、一現場で排出される土量は1立方メートル程で、都度処分場へ持ち込みがコスト面等で効率的に悪く集積場での管理が可能か等の議論を行いました。集積場では土砂の流出(水質汚濁)や乾いた時の飛散(大気汚染)に気を付ける様にレクチャー致しました。
処分場では、土砂堆積条例に該当する場合や、リサイクルにする場合の処理フローを作成し、事業者へ周知を行いました。
土砂堆積条例の対象施設の容量がひっ迫し、事業者が処分先を探すことになり、工事が中々進捗しない中、土砂リサイクル施設建設の提案を行い、建設工事業者の受け皿を確保することができました。
残土と汚泥
活動の目的・目標:建設現場から排出される残土と汚泥の違いを正しく処理できるようにすることが目的。
実施時間:2時間
実施内容:今回は、水道工事の現場から排出される土砂の処理方法を、汚泥の場合と残土の場合で比較検討を行った。汚泥が単独現場での発生量が0.1立方メートル程度なので、その都度処分場に持ち込むには、コスト的に現実的ではない。また、発生土の発生も単独現場から1立方メートル程度である。年間の工事個所が1700件あり、効率的かつ適正に処理方法を検討。
実施後の評価・感想:土砂堆積条例と廃棄物処理法を再考した。